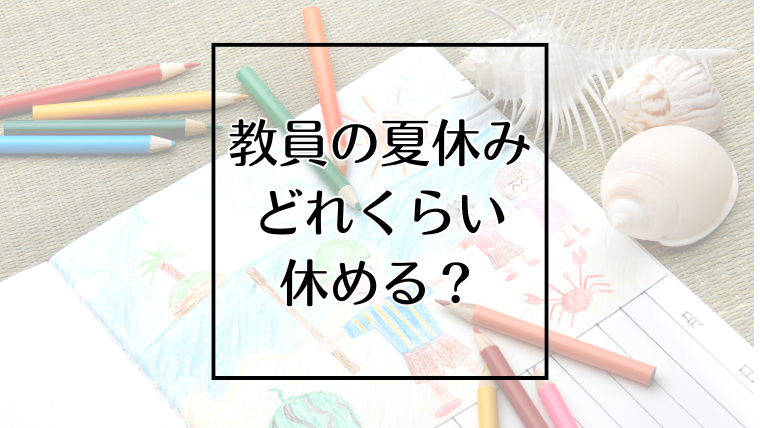【教員と民間を徹底比較】教員でもできる副業とは?

- 教員は副業ができないと聞いたけど本当なの?
- 民間企業は副業が自由なの?
- 副業観点で、教員と民間とどちらの働き方が自分に合っているか知りたい
教員という職業には、副業に関する独特のルールがあります。確かに法律で副業は制限されていますが、仕事の内容によっては副業が認めらえる場合があります。「できる副業」と「できない副業」があることを知ることが重要です。
- 11年間公立高校で勤務し、研究会運営や入試問題制作等を経験
- 副業で教科書や問題集を執筆し、50万円/年間の収入を獲得
- コロナ禍に従業員20,000人超の企業に転職し、教育事業に従事
- 現在は従業員150名程度の教育系ベンチャーで勤務
- 民間では企画職やコンテンツ制作を担当

この記事をよんでわかること
- 教員でも始められる副業の種類
- 民間企業の副業の実例
- キャリアプランや価値観にあった就職先の決め方
厚生労働省が考える副業

副業とは、本業以外に報酬を得る仕事や活動のことを指します。たとえば、休日にライターとして活動したり、平日の夕方以降にオンライン家庭教師をしたりすることも副業です。
副業の形態としては、企業に雇用される形で行うもの、起業して個人事業主として行うものなど多岐にわたります。
副業に関しては、厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」で詳しく解説されています。
ガイドラインによれば、「労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由」であり、企業が副業を制限することが許されるのは以下の4点だと説明されています。
① 労務提供上の支障がある場合
② 業務上の秘密が漏洩する場合
③ 競業により自社の利益が害される場合
④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
副業は、働き手にとってのメリットが多いと思われがちですが、企業にとってもメリットがあります。それぞれのメリットは以下の通りです。
働き手にとってのメリット
①スキルや経験を得て、主体的にキャリアを形成できるようになる
②やりたいことに挑戦し、自己実現を追求できる
③所得が増える
④小さいリスクで起業や転職の準備ができる
企業にとってのメリット
①社員が知識やスキルを獲得できる
②社員の自立性や自主性を促すことができる
③人材を獲得したり流出を防いだりして、競争力が向上する
④社員が新たな人脈を獲得することで、事業機会の拡大につながる
教員(公務員)の副業が制限されている理由

公立学校の教員は、地方公務員に該当します。そのため、地方公務員法第38条により、副業には一定の制限が課せられています。
この法律では、「営利企業への従事等の制限」が定められており、営利を目的とする企業に勤務したり、継続的に報酬を得る活動を行ったりすることが原則禁止されています。
この制限の背景には、以下のような理由があるようです。
①業務の能率を確保するため
②公正性を確保するため
③公務員の品位を保持するため
地方公務員の働き方に関する分科会による「地方公務員の兼業について」に解説があるので、詳しく知りたい方は以下の資料をご覧ください。
一方、私立学校の教員は地方公務員ではありません。したがって、副業については各学校法人の就業規則に基づいて判断されます。就業規則で認められている場合、比較的自由に副業を行うことが可能です。
教員でもできる副業
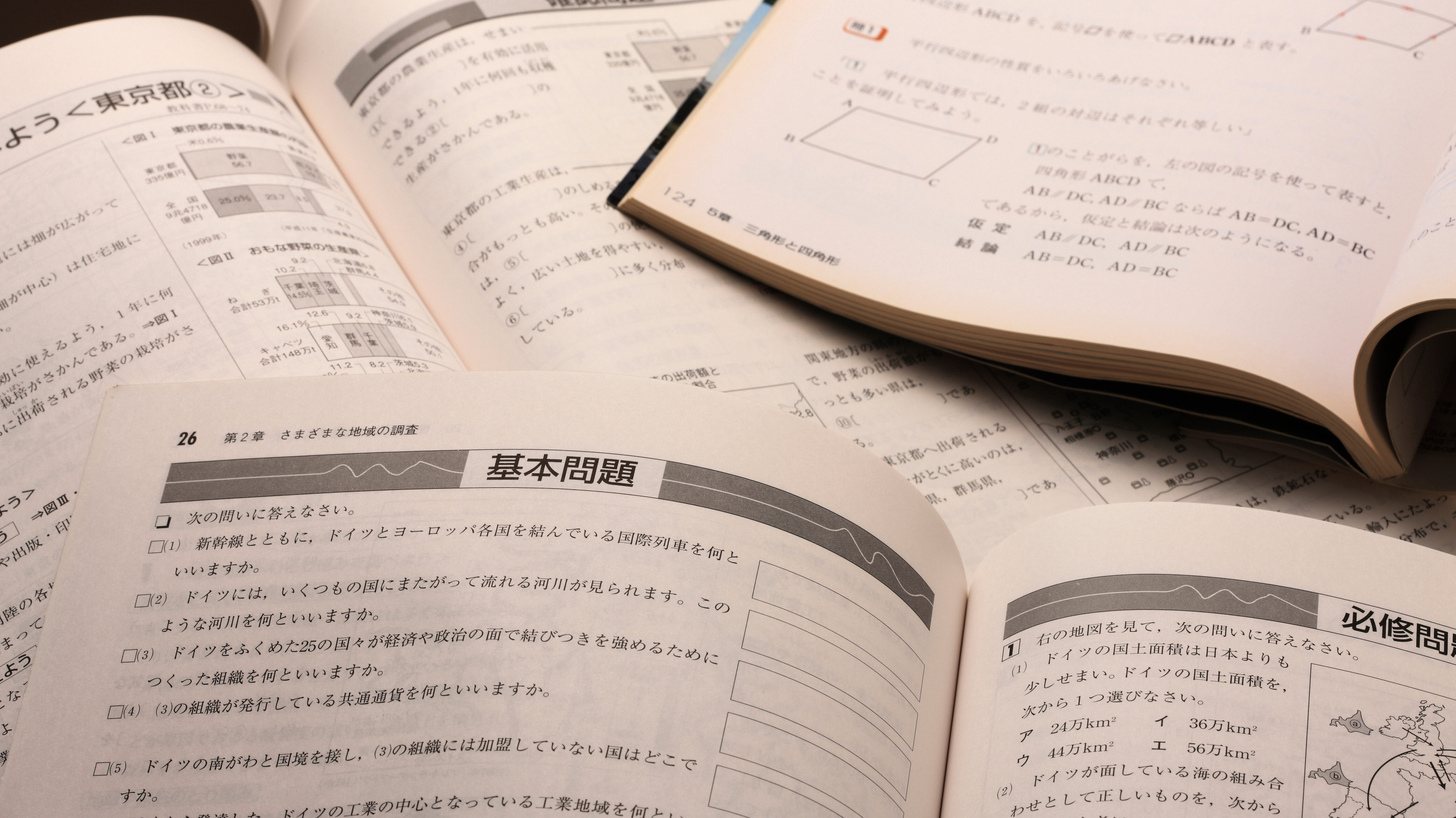
教員でも法律に抵触しない範囲であれば、副業は可能です。ただし、自治体への申請と許可が必要ですので注意をしてください。
教員ができる副業の中でも、特におすすめなのが「執筆業」です。
出版社と業務委託契約を結び、問題集など原稿を執筆することができます。執筆は、教育に直接関わる内容であり教員の能力を開発するものでもあるため、許可が下りやすい傾向があります。
学校で使用する、いわゆる副読本や演習のワークなどを執筆するイメージです。業務内容は、素材選定、問題制作、解説執筆、校正などです。
報酬の形態は主に2つあります。1つは「印税形式」で、書籍の販売部数に応じて報酬が支払われます。もう1つは「買い取り形式」で、一定額の報酬が決まって支払われます。
教科書の執筆では、印税形式の場合、毎年安定した収入を得ることも可能です。年間100万円以上の印税収入を得ている教員も実際に存在します。
教科書の執筆協力者として活動する場合、謝礼は定額であることが多いですが、信頼と実績を積めば将来的に執筆者として採用されるチャンスもあります。
執筆者は教科書に載せる教材の選定や「学習の手引き」などを執筆し、執筆協力者は素案に対して意見を具申する役割です。
私自身は、執筆協力者として教科書に携わってきました。教科書の巻末に自分の名前が載ることも非常に名誉なことです。
教員が執筆業に携わる方法
執筆業に携わるには、まず出版社との接点を持つ必要があります。そのためには、既に執筆を行っている先輩教員から紹介を受けるのが最も効率的です。
出版社は信頼できる教員に仕事を依頼する傾向が強いため、紹介を通じて信用のあるルートに乗ることが重要です。
紹介を受けるためには、以下のような活動に参加するとよいでしょう。
- 教科研究会や教科部会
- 勉強会や教育関連のセミナー
また、教科書の執筆を目指す場合は、まず「指導書」の執筆に携わることが一般的なステップです。
指導書の執筆では、納期を厳守すること、相手の期待を超える内容を提供することが求められます。そうすることで出版社からの信頼が高まり、継続的な依頼につながります。
納期を守ることは当然のことのように感じるかもしれませんが、締め切りを守らない教員は少なくありません。ベテランの先生は、メールを見ることすらあまりしません。
きっちりと締め切りを守り、レスポンス早く仕事を進めてくれる先生は、出版社にとってありがたい存在なのです。
民間企業では副業が当たり前になりつつある
近年、多くの民間企業が副業を解禁し始めています。その背景には、終身雇用制度の終焉や働き方改革があります。
民間企業の副業の実態を知るには、「副業・兼業に取り組む企業の事例について」(厚生労働省)という資料が参考になります。
特徴的な企業をいくつか挙げてみます。
・カゴメ株式会社
副業が認められるのは、生産性の高い社員のみという点が特徴的です。「生産性が高い」というのは曖昧だなと思いましたが、「年間総労働時間が1900時間未満かつ月平均の時間外労働15時間以下」という設定がなされています。
ゆとりを持って本業をこなせない人が、副業などできるはずもないので、労働者にとっても企業にとっても有効な基準だと感じます。
・SMBC日興証券株式会社
副業が認められるのは、入社4年目以降の正社員のみです。入社3年目までは本業に必要な知識の獲得やスキルの形成に注力すべきという考えから、制限が設けられているとのことです。
大学在学中からインターンシップに取り組んでおり、就職後も続けて副業を続けようと思っている人も少なくありません。就職を希望する企業が、入社何年目から副業を解禁しているかを調べることが重要です。
企業にとっても副業を認めることで、社員の満足度向上や離職率の低下といった効果があります。副業を行う従業員が本業でも成果を出しているという報告もあり、好意的に受け入れられる風潮が広まりつつあります。
副業のメリットとデメリット
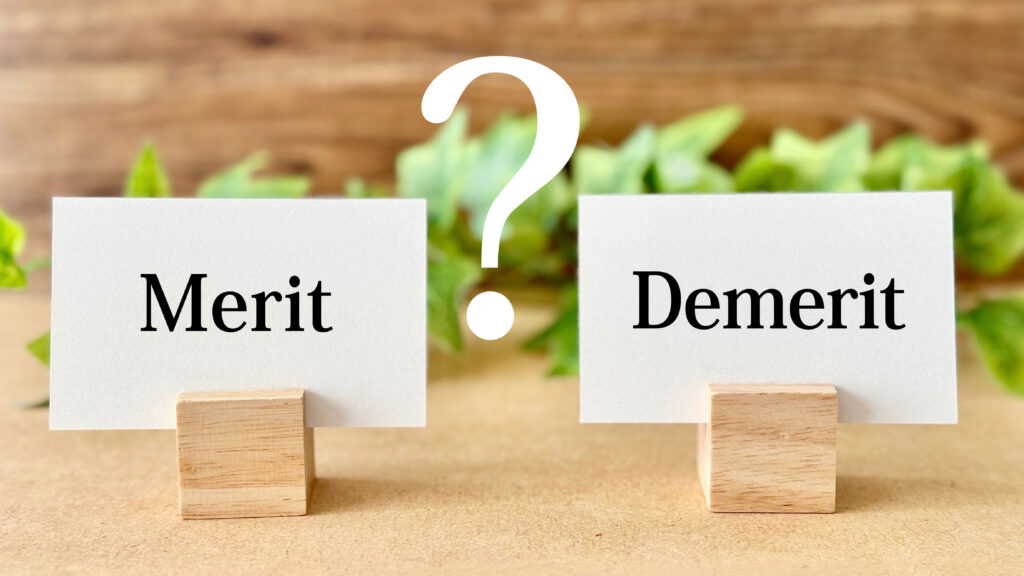
| 視点 | 教員の副業 | 民間企業の副業 |
| メリット | 自己研鑽になる 教育実践が活かせる 指導力が上がる | キャリアの幅が広がる 本業に新たな視点を持てる 人脈形成が進む |
| デメリット | ほとんどの仕事に従事できない 許可に時間がかかる | 労働時間の管理が難しい 競合では働けない |
教員の副業では、特に法律面での制約が大きいため、事前の確認が不可欠です。一方、民間企業の場合は柔軟性が高いものの、時間や体力の管理が課題となります。
民間企業の場合、兼業先の企業の事業内容が、本業の会社と似ていると、「競合」という理由で許可が出ないことがあります。大企業であればあるほど、様々な事業を抱えており、不許可の可能性が高まるので、注意が必要です。
副業を成功させるポイント

副業を成功させるためには、まず法律や勤務先の規定を正しく理解することが必要です。特に教員の場合は、地方公務員法の制限に加えて、教育委員会への届け出や許可が必要なケースが多くあります。
無許可での副業は懲戒処分の対象にもなりかねません。法的なリスクを避けるためにも、必ず適切な手続きを踏みましょう。
次に、自分の強みや関心のある分野で副業を選ぶことが成功の鍵となります。教育関係の執筆や教材制作、研修講師といった業務であれば、これまでの経験や知識が活かせるため、無理なく取り組めます。
副業は「本業の延長線上」で考えることで、スムーズに始めやすく、結果として高い成果を出しやすいです。自分の専門性を活かせる副業を選びましょう。
また、いきなり大きな仕事を狙うのではなく、小さな仕事から始めて実績を積み上げることが大切です。実績が評価されれば、次第に大きな案件にもつながっていきます。小さな成功体験を積み重ねることで、自信とスキルを同時に身につけられます。
信頼関係を築く姿勢も不可欠です。納期を守る、連絡を丁寧にする、相手の意図をくみ取った対応を心がけることで、継続的な仕事の依頼が増えていきます。
最後に、時間管理を徹底することです。副業にのめり込みすぎて本務に支障をきたすことは、本末転倒です。自分のスケジュールを冷静に見直し、「この日は副業の作業をする」「この時間は家族と過ごす」など、明確に線引きをすることが、副業を継続するうえでの安定につながります。
まとめ
民間企業はもちろんのこと、教員にも、法律に則った形であれば副業の道が開かれています。特に執筆業は、本務の延長線上で実践でき、自己成長にもつながります。
副業をしたいと考えている方は、お金を稼ぎたいのかスキルをつけたいのか、はたまた人脈を広げたいのか等、副業の目的を考えることから始めることをおすすめします。
副業の目的に照らしたときに、教員を選ぶのがよいのか、民間を選ぶのがよいのかが見えてくるはずです。