【2025年度完全版】教採小論文の書き方を知りたい【採点基準表をもとに解説】
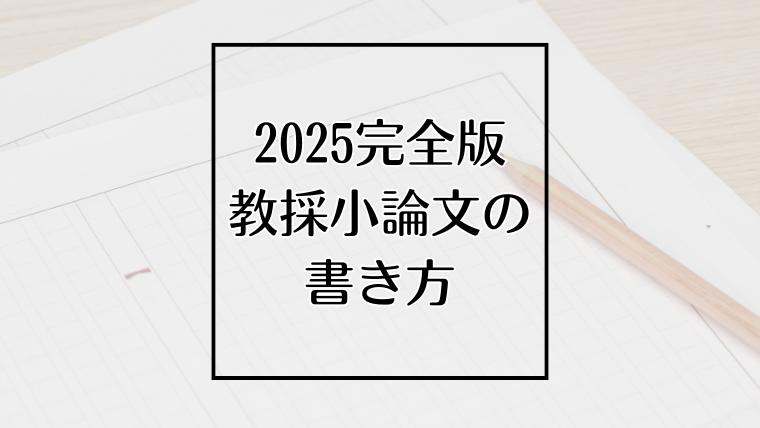
- 小論文の書き方がわからず、いつも時間内に書き終わらない…
- 採点基準がわからないので、どう書けばよいのかわからない…
- 小論文は最小限の時間で、最低限減点されない答案を書きたい
「書き方を知らない」「評価の観点がわからない」といった理由で、得点を伸ばせない受験生は多くいます。試験本番で、減点されない答案を書きあげるためには、採点基準を理解することが重要です。
- 11年間公立高校で勤務し、研究会運営や入試問題制作等を経験
- 副業で教科書や問題集を執筆し、50万円/年間の収入を獲得
- コロナ禍に従業員20,000人超の企業に転職し、教育事業に従事
- 現在は従業員150名程度の教育系ベンチャーで勤務
- 民間では企画職やコンテンツ制作を担当

この記事を読んでわかること
- 「結論→理由→ビジョン」という構成での書き方
- 小論文の採点基準
- 小論文の勉強方法
小論文は【結論→理由→ビジョン】の構成で書く
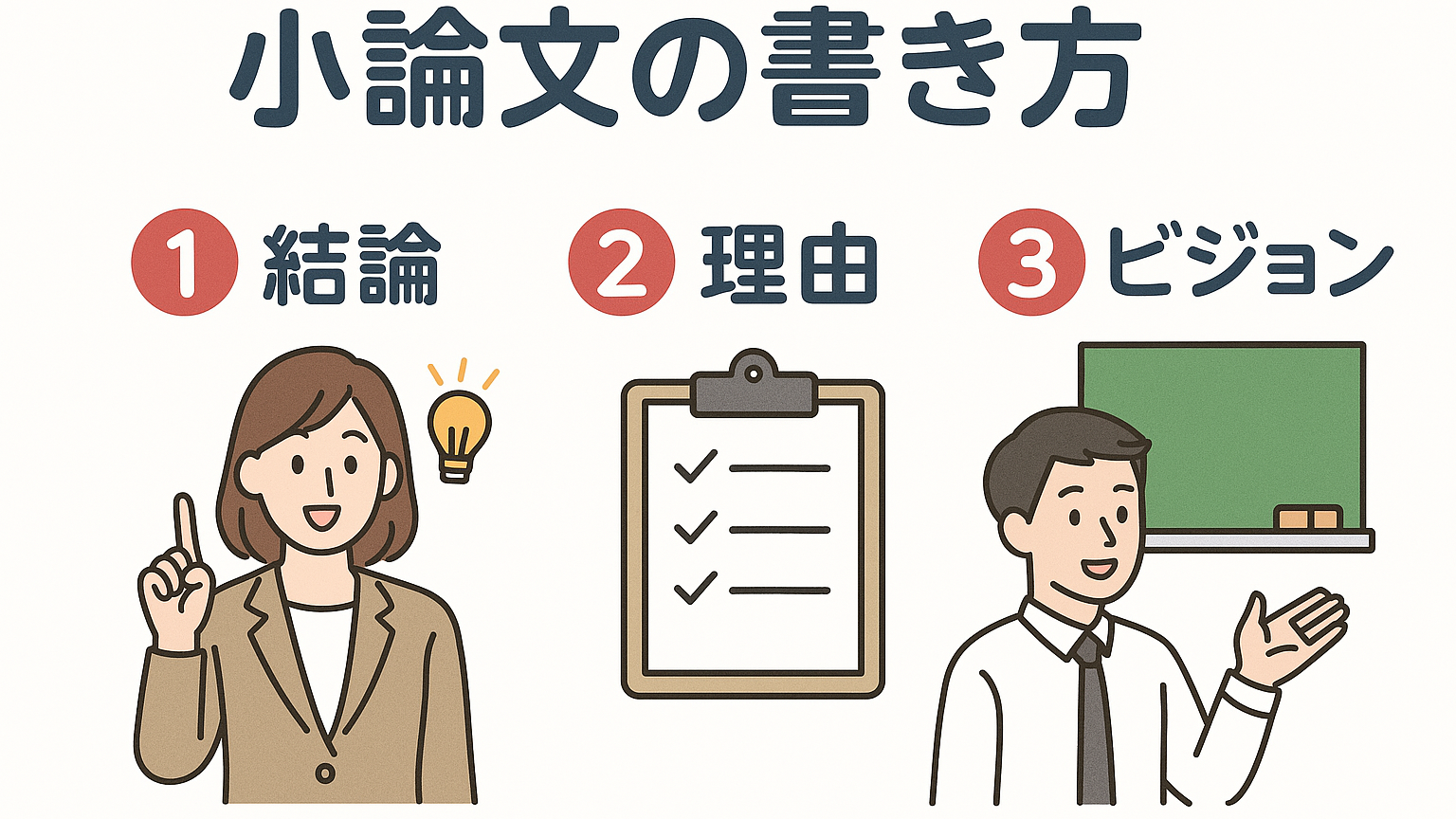
小論文は「自分の意見を、論理的に構成して伝える」文章です。そのためには、ただ思いついたことを書くのではなく、「型」に沿って論を展開することが必要です。
基本的で汎用性が高い構成が「結論→理由→ビジョン」の三段構成です。
結論:問いに対する答え
第一段落では、設問に対する自分の意見を端的に述べます。
ポイントは「結論ファースト」です。冒頭で「自分はこう考える」とはっきり述べましょう。結論を後回しにすると、読み手(採点者)に伝わりづらくなります。
たとえば、「私は学校教育において探究的な学びを重視すべきであると考える」などのように、問いへの明確な回答を最初に書き出します。
問いを的確にとらえることも重要です。何が問われているのかを冷静に判断したうえで、回答を始めましょう。
設問の意図を捉えそこなったり、論点をずらしたりすることも厳禁です。たとえば、「探究的な学びの重要性を述べよ」に対して、「そもそも探究的な学びは必要がない」のような回答です。
理由:結論を支える根拠
第二段落では、結論を支える理由を述べます。この理由の部分が、答案全体の説得力を左右します。
理由の提示には二つの方向性があります。
一つは「主観的な根拠」、もう一つは「客観的な根拠」です。
主観的根拠とは、自分の実体験や観察をもとにしたものです。たとえば、「教育実習の現場で考えたこと」「大学4年間の学びを通して感じたこと」などが該当します。
一方、客観的根拠は、ニュース・中教審の答申・統計データなど、広く社会に共有されている事実をもとに論じる方法です。大学4年間での研究実績でもよいでしょう。
制限字数にもよりますが、主観と客観のどちらか一方だけでは説得力に欠けることがあります。最も強い理由パートは、この両方をバランスよく組み合わせたものです。
ビジョン:未来に向けての行動・提案
最後の第三段落では、「第一段落で述べた意見をもとに、どう行動していきたいか」を述べます。教員採用試験の小論文なので、教員になった後のビジョンを語るのが一般的です。
この部分に印象を残すためには、抽象的な理念ではなく、具体的な行動を示すことが大切です。
「どうしたいか」「何を改善したいか」「自分の職務としてどう実現するか」などを述べるとよいでしょう。
たとえば、「教員として、年間を通じて探究型の学習を授業に取り入れ、定期的に生徒の振り返りの時間を設けることで、自ら学ぶ力を育てていきたい」といったように、自分の行動にまで落とし込むことが求められます。
このようにして「結論→理由→ビジョン」の三段構成をしっかり押さえることで、読み手に伝わりやすく、評価されやすい小論文が書けるようになります。
評価される小論文とは?7つの採点基準を解説
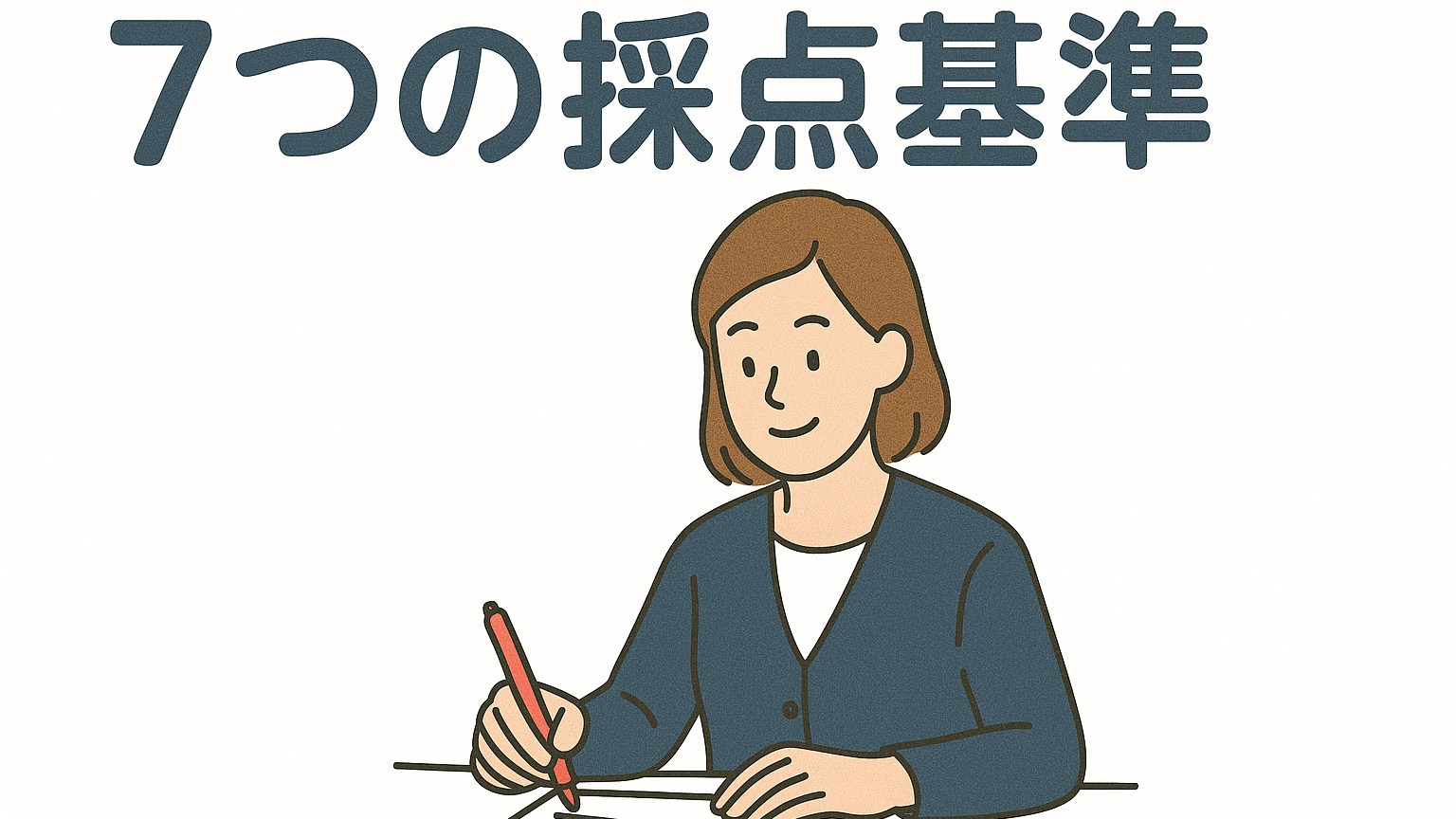
採点者は複数の観点から総合的に評価しています。一般的な採点基準について、解説します。
①制限字数
必要字数を満たしているかが見られます。
9割以上書けていないと、そもそも評価の土台に乗らないと考えたほうがよいでしょう。特に教員採用試験は字数が少ないため、回答欄を全て埋めるくらい論じてはじめて、他の受験生と差別化ができます。
冗長に論じるのではなく、密度の濃い文章を書くようにしましょう。
②問いへの対応
設問で問われていることに対する結論を述べることが必要です。
当たり前のように聞こえますが、問いを捉え損ねたり、論点をずらしたりする回答は散見されます。設問に答えていない答案は0点になるので、注意が必要です。
③結論とビジョンの具体性
第一段落の結論や最終段落ビジョンは具体的である必要があります。具体性の強さは独自性につながります。小論文では「あなた」にしか書けない内容を述べることが重要です。
「学校教育の発展に貢献したい」などの理念だけを述べたり、批評家になりきって他人事として述べたりするのは避けましょう。「生徒の主体的な学びを促進するために、各授業の最後に振り返りの時間を設け、生徒自身が学びを次につなげていけるようにします」など、具体的に論じるようにしましょう。
④根拠の強さ
理由の部分では、主観的な内容だけでなく、事実や客観的な事柄を書くことで、根拠を強めることができます。
制限字数にもよりますが、主観と客観のどちらか一方だけでは説得力に欠けることがあります。最も強い理由パートは、この両方をバランスよく組み合わせたものです。
⑤論理展開の適切さ
論理が飛躍したり、破綻したりしていると採点自体が難しく、0点になる可能性があります。
結論→理由→ビジョンがつながっていることが必要です。結論と挙げた具体例の結びつきが弱かったり、結論とビジョンが微妙にずれたりすることはよくあります。
これに陥ってしまう人は、書き始める前に構成をメモすることが必要でしょう。
⑥論の明快さ
「一度読めば内容が分かる」を目指してください。採用試験では、多くの小論文を採点します。そのなかで、「なんだかよくわからない文章」が出てくると、採点者にとっても大きなストレスとなります。
一文が長すぎない、重複や無駄がない、指示語を使わず、主語述語を明確に。
これらの工夫を通して、読み手が一度読めばわかる文章を目指してください。
⑦表現の正確さ
たかが誤字脱字、と思われるかもしれませんが、正しい日本語で正しく内容を伝えることは、教師にとって必要不可欠のスキルです。
次のコラムで、表現上の減点項目を解説します。
減点されないための表現ルール7選

表現の減点は、内容と関係なく差がつくポイントです。
特に以下のルールを守ることで、確実に減点を避けることができます。
- 誤字がない
教諭として~
教輸として~ - 脱字がない
授業で用いる教材は、プリントと~
業で用いる教材、プリントと~ - 話し言葉を使わない
しかし、この意見には~
でも、この意見には~ - 文体を統一する
~することが必要だ。なぜなら~からである。
~することが必要です。なぜなら~からである。 - 一文を短くする
主体的な学びを引き出すことが必要だ。なぜなら、~からである。
主体的な学びを引き出すことが必要であり、理由は~からである。 - 主語と述語のねじれを防ぐ
私の理想は、~な教師になることである。
私の理想は、~な教師になりたい。 - 呼応表現を正しく使う
全く~ない。
全く~だ。
これらはテクニック以前の「基本動作」であり、守ることで減点を防ぎます。
【2025完全版】小論文の採点基準表
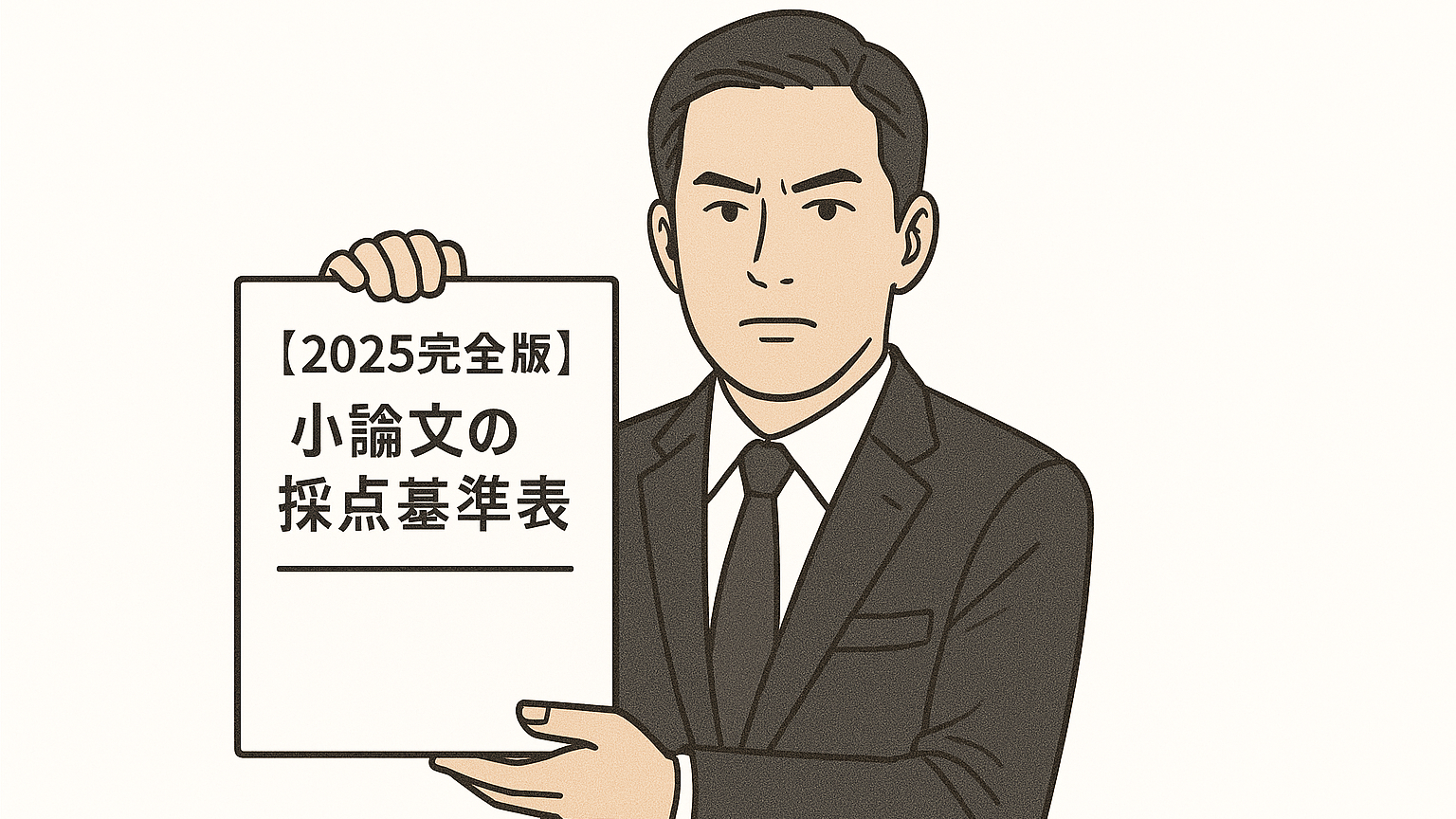
ルーブリック形式で採点基準表を作成しました。小論文は、他者より抜きん出たものを書くことが非常に難しいため、まずは減点されない答案を目指しましょう。
評価はシンプルに三段階です。まずはBを目指しましょう。
A)他の受験生より優れている
B)他の受験生と同等である/最低限必要な内容が書かれている
C)他の受験生より劣っている/最低限必要な条件を満たしていない
| 観点 | 着眼点 | A評価 | B評価 | C評価 |
|---|---|---|---|---|
| 制限字数 | 必要字数を満たしているか | なし | 制限字数の9割以上を書いている | 制限字数の9割未満である |
| 問いへの対応 | 設問と結論が対応しているか | なし | 設問文で問われていることに対する結論を述べている | 設問文で問われていることに答えていない/論点をずらしている |
| 結論やビジョンの具体性 | 結論やビジョンに具体性があり、独自性を生み出しているか | 結論やビジョンの具体性が強く、独自性がある | 具体性のある結論やビジョンを述べている | 結論やビジョンの抽象性が高く、言いたいことが伝わらない |
| 根拠の強さ | 主観的な内容に偏ることなく、客観的な内容を書くことで根拠を強めているか | 社会的に重要度の高い出来事や客観的なデータなどをもとに根拠を述べている | 自身の経験をもとに根拠を述べている | 主観性や個別性が強く根拠として成り立たない/根拠として挙げたことが事実ではない |
| 論理展開の適切さ | 論が飛躍していないか | なし | 飛躍のない展開となっている | 論理が破綻したり、飛躍したりしている |
| 論の明快さ | 読み手に伝わりやすいか | なし | 読み手に負荷のない文章が書けている | 冗長な内容や無駄が多く、読み手が疑問を持つ内容である |
| 表現の正確さ | 表現上の減点項目がないか | なし | 減点項目が3つ以下である | 減点項目が4つ以上ある |
A評価が「なし」となっているものは、Bであることが当たり前であるためです。まずは全てB評価をとることを目標にしてください。
それぞれのパートで何文字書くか
制限字数に応じて、各パートの字数を調整します。構成例は以下の通りです。
| 字数 | 結論パート | 理由パート | ビジョンパート |
|---|---|---|---|
| 400字 | 50字 | 250字 | 100字 |
| 800字 | 150字 | 400字 | 250字 |
| 1000字 | 150字 | 600字 | 250字 |
理由とビジョンは、字数に応じて内容を厚くします。
【理由パート】
・字数が多い場合は、理由を二つ書く
・理由を二つ書く場合は、主観的な内容と客観性のある内容を書くとよい
・客観的な根拠を書くことで、結論で述べたことの重大性を補強できる
【ビジョンパート】
・字数が少ない場合は、やや抽象度の高いビジョンで収めるとまとまりがよくなる
(字数が少ないと具体的な内容を書ききることができない)
・字数が多い場合は、「抽象的なビジョン+具体的な取り組み」で構成する
書くだけじゃダメ!小論文の正しい勉強法
小論文は書くだけでは伸びません。以下の手順を繰り返すことが実力アップの近道です。
①過去問や問題集の問題を解く
②自己採点をする
③他者に採点してもらう
④自身と他者との採点をすり合わせ、採点基準への理解を深める
⑤書きなおす
特に④が重要です。答案を書いた後、すぐに誰かに添削を依頼するのではなく、まずは自己採点をしてください。そのうえで他者に採点を依頼しましょう。

「自分ではAだと思ったけど、他者が見るとBなのか…」のように、すり合わせを繰り返すことで自分の答案をより客観的に見ることができますし、採点基準への理解も深まります。

なるほど!採点してくれる人がいないと小論文の対策ができないと思っていたのですが、自分でも採点できるようになることが重要なんですね!
採点基準を理解することで、本番でも減点されない、適切な答案が書けるようになります。
まとめ|今すぐ書き始めよう!
この記事では、小論文に必要な構成・評価基準・勉強法を網羅的に紹介しました。
重要なのは、「結論→理由→ビジョン」という構成を毎回踏襲し、他者との対話の中で採点基準を内面化していくことです。
まずは、受験する予定の自治体の過去問を解くところから始めてみましょう!
